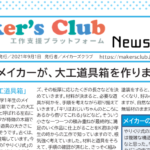大工道具箱風小物入れの製作
調べるだけでなく、自分で試して体験もしてみる。
素晴らしいですね。
材料と用意するもの
材料
- 化粧くぎ
- 25mm長さ。
- くぎの長さは、打つ板の厚さの2.5~3倍くらいが目安です。
- 多めに入っています。
- 板 11枚(板厚は9mmです。)

※フタの取っ手の部材の長さが間違っています。写真を差し替え予定。
針葉樹なので柔らかく、下降がしやすい木材です。色も薄い黄みがかった白色で、木工作の作品を引き立てます。
2x4材なども、この材料です。
自分で準備しておくもの
必要なもの
- 筆記用具(線を引いたりする時に使います。)
- げんのう、または、金づち
- 直定規(普通の定規)
- 三角定規(直角かどうかを調べるのに使います)
- ノコギリ(ノコギリカッターでもよいです。ベニヤ板を切ります。)
- キリ(くぎを打つときの下穴をあけます。)
- 要らない板(キリを使う時の下敷きに使います。)
- 木工用ボンド
あると便利なもの
- 塗れ雑巾
- キリを使う時に手を濡らしたり、はみ出した接着剤を拭きとったりします。
- 小刀、または、カッター
- 面取りに使えます。
- 彫刻刀
- 面取りに使えます。
製作

製作は、オンラインで2日間の個別指導で行いました。
もともと工作好きで、模型を入れるためのショーケースを自作した経験のあるK君。集中して作成しました。
寸法どりも定規やさしがねを使って手際よく進めて行きます。
さしがね(差し金)
聖徳太子の時代から存在したとも言われているL字型の定規です。

「差金(さしがね)」は、「上棟式」の時に、「墨壷(すみつぼ) 」、「釿(ちょうな;槍がんな)」とともに供えられる「大工道具の三種の神器」の一つです。
上棟式は、土台作り、柱、棟、梁などの基本構造が完成した後に、棟木を上げるときに行われる行事です。
本体の枠を作る
印をつける
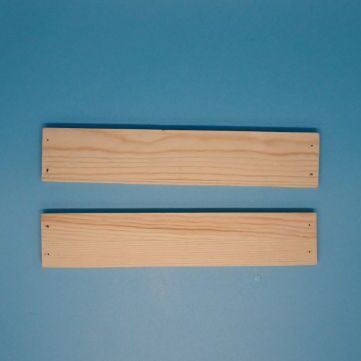
キリで穴をあける。
濡れタオルなどで手を濡らしながらすると力が入りやすいです。

キリは、両手で下へ押しつけながら回していきます。
木材とキリが垂直になるようにキリを当てて、キリを回転させても軸が動かないようにします。回転させてしまうと、穴が大きくなってしまい、くぎを打っても穴が見えて不格好になります。
穴を板の表から裏まで通してあける時、キリの先が穴をあけている木材を突き抜けるので、必ず下に当て木をしましょう。
本体の側面枠を作る


他の3か所も同様にくぎを打ちます。


最後の長手方向の板をくぎ打ちするときは、対角線の位置の順にくぎを打つと、ずれにくくなります。
くぎを打つ平たい面の「つち」をもつ金属製のものを、「かなづち」、「かなづち」のうち、くぎを打つ面の一方が平らで、もう一方が、ほんの少し丸く凸状になったものを「げんのう」と言います。
木工作では、げんのうをよく使います。
最初は、平らな面でくぎを打っていきます。
げんのうの頭が、くぎにまっすぐ当たるように打ち下ろします。ななめに当てると、くぎが曲がってしまうので注意します。
くぎの頭がほとんど木材の表面に打ち込まれたら、げんのうの丸い面でくぎを打ちます。こうすると、表面に傷をつけずにくぎを打ちこむことができます。
底にくぎの穴をあける
- 穴の位置に印をつける。
- キリで下穴をあける。

底板に側面の枠をくぎ打ちする



本体の取っ手とフタ押さえ板を付ける





フタの横幅を本体の内側の幅に合わせる
粗めの紙やすりを使って、軽々とフタが本体内側に入れるように、フタの横幅を整えます。
このとき、紙やすりを平らな机などに置いて、その上を、車を走らせるようにフタの長手方向の辺をこすりつけることでやすりをかけると真っ直ぐに書けやすいです。
フタの幅を、本体の幅より少し(0.5~1mm)小さめの幅にしておくと、滑らかに動くようになります。
フタに「一つ目の」取っ手を付ける
- フタを奥まで当てて、フタの押さえ板の縁のところで線を引く。
- この時の長さは、作品それぞれに微妙に違ってくるので、実物に合わせて位置を決めます。
- フタの取っ手の木材に木工用ボンドを塗る。
- フタの取っ手の木材の外側の面を先程付けた印の線に合わせて、フタに貼り付けます。
- この時、左右の突き出した部分が同じ長さになるように注意します。接着剤が乾く前に、箱にセットしてみて、取っ手の両端と、本体の側面の外側の両方の面が一致するように、微調整します。
- フタの取っ手はくぎ打ちはしません。接着剤で固定するだけです。
フタの取っ手をフタに接着剤で貼り付けて接着剤の乾燥を待っている間に、
「フタが滑らかに動くようにするための工夫の作業」をしておくとよいです。
フタの長さを決めて「2個目」の取っ手を付ける
日本のノコギリは、押す時ではなく、引くときに切れます。木目によって、「横刃」と「縦刃」があり使い分けます。木目に平行な方向に切る時は、「縦刃」を使い、木目に垂直な方向に切る時は、「横刃」を使います。ノコギリで木材を切る時に気を付けることを書きます。
まず、ノコギリを力を入れて握らず、軽く人差し指を柄の上側に沿えて持ちます。ノコギリを引くときも、力は強くは入れず、極端に言えば、下方向へは重力分の力がかかるだけぐらいの気持ちで、前後に引くことに力を使います。切る時に、まっすぐ切れているかどうかを真上から確かめながら切ると、曲がらずに真っ直ぐ切れます。曲がっていないかな?と不安になっても横からのぞきながら切手はいけません。曲がって切ってしまいます。覗き込みたい時は手を止めましょう。
完成
フタのロックがかかっている時

フタのロックが解除された時

フタを取り出しているところ

工夫
よりかっこよく、美しく仕上げるための工夫を紹介します。
角(かど)の面取り
塗装をする
水性塗料で塗装をすると美しく、汚れにくくなります。
フタが動きにくい時
フタのロックを開閉するときに、動かしにくい場合は、
本体の上の面を、小刀などで少し削ると滑らかに動くようになります。
フタ押さえの縁から30mmぐらいまでのところの本体の上の面を鉛筆で薄く塗っておいて、その鉛筆が消えるまで、小刀かカッターで、薄く削って行きます。鉛筆の跡が無くなったら、一度、フタを差し入れてみて、動きやすさを確認します。

フタの取っ手を接着剤で貼り付けた後、乾燥を待っている間に、この作業をすると、効率よく時間を使うことができます。
この大工道具箱風小物入れを作りたい人へ
この工作に興味のある方に、必要な材料を詰め合わせたセットを実費で提供しています。「Maker’s Clubお問合せページ」からお問合せください。